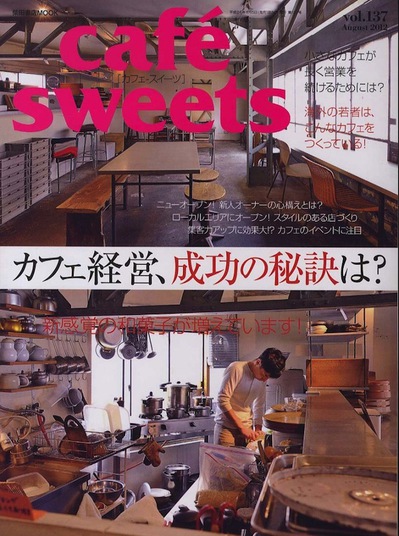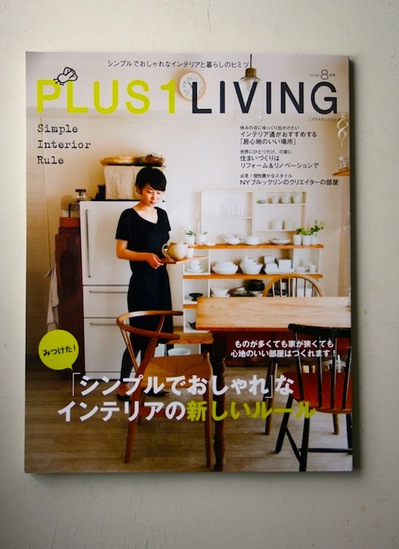大阪の国立文楽劇場内には、文楽について学べる展示もある
たぶんこのクボマガを読んでくださっている方の中で文楽(人形浄瑠璃)に興味のある方は少ないと思うんだけど、先日ツイッターで文楽について興奮気味につぶやいてしまったので、自分の中で考えをまとめるために書いてみます。よろしければ、お付き合いを。
そもそも私が文楽についてツイートしたきっかけは、橋下大阪市長のツイッターを目にしたから。
そこには「なんで人間国宝の人形遣いの皆さんは、顔を出されるのか。文楽は人形の芝居のはず。心中の最後のクライマックスで、人形遣いの皆さんの顔が、人形の横にあると、舞台に入り込めない。(略)」とあって、それに強烈な違和感を覚えたの。
私はむしろ、人形劇なのに主役の人形を遣っている人形遣いの顔が出ている(一部の場だけね)ことのほうが、面白いなと思ってる。顔が出てるどころか、裃(かみしも)まで着けてたりする。
人形劇って世界中にいろんな形で存在しているけど、人形遣いがこんな派手な格好で出てくる形態って、ほかにあるのかな。
この感覚は、いったいどこから来たんだろうと考えると本当に面白いし、なんか日本ってすごいなーと思ってしまう。
だって、普通に考えたら顔隠すのが順当なのに、顔出しで裃。これ、たぶん西洋人にはない発想じゃない? すごく面白い。
「人形遣いが顔を出していても、演目に引き込まれるうちに人形しか目に入らなくなる」という人もいる。だけど、私にはそういう経験はない。だからといって、興醒めするかといえば、全くそんなことはない。
伝統芸能とか、芸術って「人形劇だから人形に集中すべき。だから人形遣いは顔を隠すべき」というような、理路整然とした尺度で測れる物ではないと思うのよ。
そもそも、文楽を人形劇といっていいのかどうかすら(人形浄瑠璃なんだから、人形劇でいいのかな...)私の中ではわからない。
私が初めて文楽に触れたのは、20代の頃。何の予備知識もなく東京の国立劇場に行ったら、その摩訶不思議な魅力にすっかり虜になってしまった。
文楽って、太夫、三味線、人形遣いがいて、人形がいる。もうそれだけで単なる人形劇とは言えない。
しかも、太夫と三味線はくるっと回転する床に乗って登場するし(なんかお化け屋敷みたい!)、人形遣いは顔出してるし(実は顔を見てるのも楽しい!)、語っている太夫の顔が面白くて目が離せないし(住太夫は特に!)もう、私の常識では考えられない、めくるめく世界だったの。「なにこれ、エキゾチック・ジャパン!」と思った。
で、そこから公演のたびに劇場に行くようになった。それでも私は特に文楽についてさほど勉強もせず、「エキゾチック・ジャパン!」な楽しみ方をしている。
ベルリンに来た今では、公演時期に合わせて一時帰国というわけにもなかなかいかないけど、昨年は初めて大阪公演も観に行けた。
私の鑑賞の仕方はかなり邪道かもしれないけど、鑑賞の仕方に決まりなんてないと思う。私は自分なりに文楽を楽しんでいるし、文楽が好き。
誰が、どんな見方をしたって構わないと思う。そういう点では、橋下大阪市長の「人形遣いの皆さんの顔が、人形の横にあると、舞台に入り込めない」というのも、一つの意見。そういう意見があったっていい。
ただし、もし「だから今の文楽をやめて、全公演をもっとわかりやすい演出に変えろ」と言ったとしたら(仮定)、それは違うと思う。
橋下大阪市長は、文楽が一般大衆に受け入れられていないのは(つまり興行が悪いのは)、演出や台本が古いからじゃないかと言っているらしい。だから、新しい演出があってもいいんじゃないかと。
私も、いろんな演出があっていいと思う。ただし、私は今の文楽が好きなので、それは消さずに残してほしい。
その上で、現代風の斬新な文楽があってもいいと思う。その方が楽しい人もきっといるだろうし、現代演出文楽はまた別物という感覚で楽しめるかもしれない。私は何事も、個人が選択できる状態が好きだ。
歌舞伎は観たことがあっても、文楽は未経験という人も多いんじゃない? もしよかったら一度行ってみて。好きになれなかったら、それでいい。
でも面白いんだから〜。エキゾチック・ジャパンでワンダフル、アメージングでファンタスティック! 百聞は一見にしかず、よ!